冒頭の直接回答
マイクラ(Minecraft)のコマンドは、チャット欄に「/」で始まる命令文を入力することで、時間変更・テレポート・アイテム付与などゲーム内の様々な操作を瞬時に実行できる機能です。Java版・統合版ともにチート許可設定を有効にすれば使用可能で、基本構文「/コマンド名 対象 パラメータ」を覚えるだけで初心者でも簡単に活用できます。
要点
- コマンドは「/」で始まり、チャット欄(Tキー/右十字キー)から入力して実行
- 使用にはワールド作成時または設定画面で「チートの許可」を有効化する必要がある
- /time set・/tp・/give などの基本コマンドで時間・移動・アイテム管理が即座に可能
- セレクター(@p/@a/@e/@r)とターゲット指定で複数プレイヤーやエンティティを制御
- コマンドブロックを使えば自動化・ギミック作成などの高度な仕掛けが構築できる

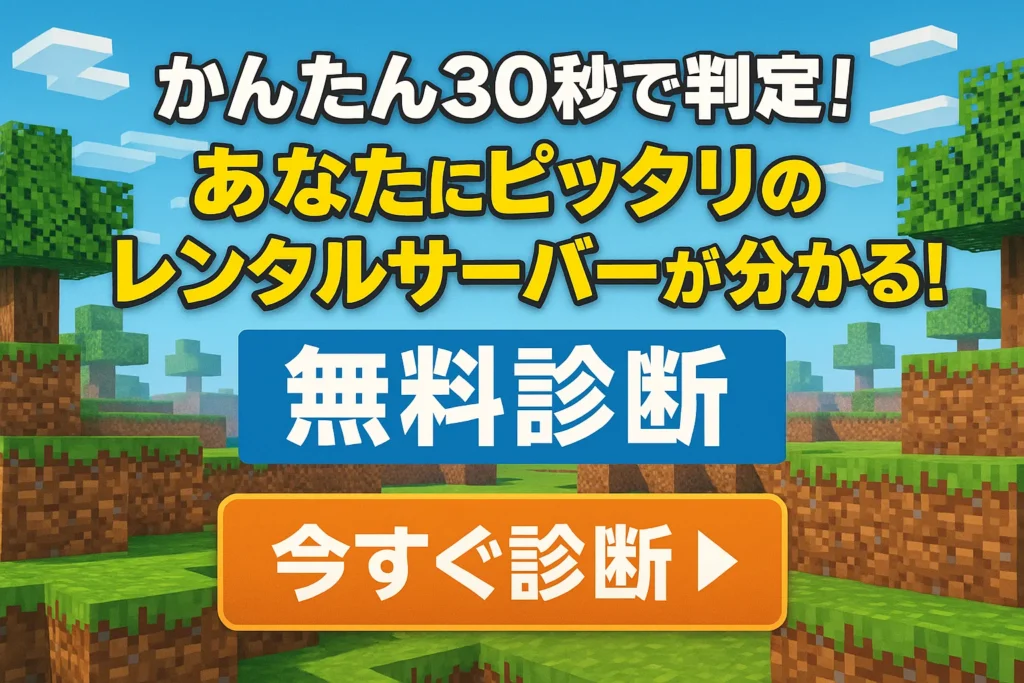
マイクラコマンドとは?基礎知識と有効化方法
コマンドは、マイクラのゲーム内で「管理者(権限を持つプレイヤー)」が使える“強力な操作機能”です。建築の効率化、イベント演出、装置の自動化、デバッグ用途など幅広く活躍します。
コマンドを使うための準備
コマンドはとても便利ですが、ワールドの状態を一瞬で変えてしまうため、慣れるまでは「テスト用のワールド」を用意するのがおすすめです。建築・整地系のコマンド(/fill や /clone など)を試すときは、事前にワールドのバックアップ(コピー)も取っておくと安心です。
また、統合版(Bedrock)では「チートの許可」を有効にすると、基本的にそのワールドでは実績(Achievements)が解除できなくなります。実績を狙うワールドと、コマンド練習用ワールドを分けておくと失敗しません。
- Java版:ワールド作成時に「チートを許可」をON(既存ワールドは「LANに公開」で一時的に有効化も可能)
- 統合版:ワールド設定で「チートの実行」をON(既存ワールドでも設定画面から変更可能)
設定後、チャット欄に「/」を入力して候補が出る状態なら準備完了です。
コマンドの基本構文と入力ルール
コマンド入力の基本操作
- PC(Java版/統合版):Tキーでチャットを開いて入力
- Switch/PS/Xbox:右十字キーでチャットを開く(環境により操作が異なる場合あり)
基本構文の構造
基本形は次の通りです。
/コマンド名 対象 パラメータ例:最も近いプレイヤーにダイヤを1個渡す
/give @p diamond 1入力時の重要ルール
- 半角スペースで区切る(スペース位置が違うとエラーになりやすい)
- スペルミス・大文字小文字に注意(Java版は特に厳密。統合版は候補表示を活用するとミスが減る)
- 座標は「X Y Z」の順(例:100 64 -200)
- 相対座標「~」は現在位置基準、ローカル座標「^」は視線方向基準
座標指定は状況に応じて使い分けます。
- 絶対座標:
100 64 -200(ワールド基準の固定位置) - 相対座標:
~ ~10 ~(現在位置からの相対位置、~は0を意味する) - ローカル座標:
^ ^ ^5(視線方向基準。Java版・統合版ともに多くのコマンドで使用可能)
Tab補完機能
Java版ではコマンド入力中にTabキーを押すと、利用可能なコマンドやパラメータの候補が表示されます。統合版では入力に応じて自動的に候補が表示されます。
コマンドの実行権限
シングルでは「チート許可」をONにすれば実行できます。マルチサーバーでは、OP(管理者)権限や権限レベルの設定が必要です(後述)。
初心者向け|今すぐ使える便利な基本コマンド10選
ここでは、覚えると「すぐ便利」な基本コマンドを厳選して紹介します。まずは“真似して実行”し、慣れたら対象(@p/@aなど)や数値を変えてみてください。
/time set(時間変更)
結論:昼・夜の切り替えが一瞬でできます。
/time set day(昼にする)
/time set night(夜にする)
/time set noon(正午にする)
/time set midnight(深夜にする)建築中に夜が邪魔なときや、夜限定イベントをすぐ始めたいときに便利です。
/weather(天候変更)
結論:雨や雷を止めたり、逆に発生させたりできます。
/weather clear(晴れ)
/weather rain(雨)
/weather thunder(雷雨)天候は視界や戦闘に影響するため、整地・建築・撮影などで重宝します。
/gamemode(ゲームモード変更)
結論:サバイバル・クリエイティブ・アドベンチャー・スペクテイターの4モードを瞬時に切り替えます。
/gamemode survival(サバイバルモード)
/gamemode creative(クリエイティブモード)
/gamemode adventure(アドベンチャーモード)
/gamemode spectator(スペクテイターモード。Java版・統合版で利用可能。統合版は一部挙動に制限がある場合あり)
短縮形も使用可能:/gamemode s、/gamemode c、/gamemode a、/gamemode sp
他のプレイヤーのモードを変更する場合は、コマンドの末尾にプレイヤー名を追加:/gamemode creative PlayerName
/tp(テレポート)
結論:好きな座標や他プレイヤーの元へ一瞬で移動できます。
/tp PlayerA PlayerB(PlayerAをPlayerBの場所へ移動)
/tp @p 100 64 -200(最も近いプレイヤーを座標へ移動)
/tp @s ~ ~10 ~(自分を10ブロック上へ)落下死の回避、迷子の救助、施設間ワープなどに使えます。座標移動は事前に現在地をメモしておくと戻れます。
/give(アイテム付与)
結論:指定したプレイヤーにアイテムを付与します。
/give @p diamond 64(最寄りのプレイヤーにダイヤ64個)
/give PlayerName minecraft:diamond_sword 1(Java版は名前空間が付く場合あり)配布ワールドやイベントで「参加者に配布」が一瞬でできます。誤配布防止に、まずは count=1 など小さめで試すのがおすすめです。
/summon(モブ・エンティティ召喚)
結論:モブやエンティティを好きな場所に召喚できます。
/summon zombie(ゾンビ召喚)
/summon creeper ~ ~ ~(現在地にクリーパー召喚)
/summon lightning_bolt(雷を発生)検証・撮影・ミニゲーム制作で便利ですが、過剰召喚は処理落ちの原因になるので注意してください。
/kill(エンティティ削除)
結論:プレイヤーやモブなど指定対象を削除(キル)します。
/kill @e[type=item](落ちているアイテムを全削除)
/kill @e[type=zombie,distance=..20](20ブロック以内のゾンビを削除)
/kill @s(自分をキル)誤爆しやすいコマンドなので、type・distance・tag で対象を絞ってから実行してください。
/effect(ステータス効果付与)
結論:スピードや透明化などの効果を付与できます。
/effect give @p speed 30 1(最寄りにスピード30秒 レベル2相当)
/effect give @s invisibility 60 0(自分に透明化60秒)
/effect clear @p(最寄りの効果を解除)イベント演出や“鬼ごっこ”などミニゲーム制作で特に活躍します。
/setworldspawn(ワールドスポーン設定)
結論:ワールドの初期スポーン地点を変更します。
/setworldspawn(現在地をワールドスポーンに)
/setworldspawn 0 80 0(指定座標をワールドスポーンに)配布ワールドやサーバーのロビー設定で必須級です。プレイヤー個別のスポーンは /spawnpoint を使います。
/gamerule(ゲームルール変更)
結論:ワールドのルールを細かく変更できます。
/gamerule keepInventory true(死亡時にアイテム保持)
/gamerule doDaylightCycle false(時間を止める)
/gamerule mobGriefing false(クリーパーの爆発被害など)検証ワールドは keepInventory をONにするとストレスが減ります。イベントや建築用途では mobGriefing をOFFにするのも定番です。
セレクターとターゲット指定の使い方
セレクター(@p/@a/@e/@r)を使うと、プレイヤー名を直接入力せずに対象を指定できます。コマンド上達の近道は「対象指定の理解」です。
基本セレクター
セレクターは「対象の絞り込み」を覚えると一気に実用度が上がります。よく使うのは次の引数です(Java版・統合版で細部が異なる場合があります)。
type=:種類で絞る(例:@e[type=creeper])distance=/r=:距離で絞る(例:@e[type=zombie,distance=..10])tag=:タグで絞る(装置作りで必須。例:@e[tag=boss])scores=:スコア(scoreboard)条件で絞る(例:@a[scores={kill=10..}])sort=nearest/random、limit=1:複数ヒットしたときの選び方
特に tag と limit は、コマンドブロックで「対象が多すぎて処理が重い」「狙った1体だけに当たらない」といった失敗を防げます。
@p:最も近いプレイヤー@a:全プレイヤー@r:ランダムなプレイヤー@s:コマンド実行者(自分、またはコマンドブロック自身)@e:全エンティティ(モブ/アイテム/矢など)
例:全員をクリエイティブにする
/gamemode creative @aターゲット引数(条件指定)の基本
セレクターには引数を付けて対象を絞り込めます。例えば、半径10ブロック以内のゾンビだけを削除する場合:
/kill @e[type=zombie,distance=..10]距離指定は「..10(10以下)」や「5..(5以上)」のように範囲指定が可能です。
コマンドブロックの入手と活用方法
コマンドブロックは、コマンドを“自動で実行”できる装置です。ミニゲーム、トラップ、演出、ワープ装置などに欠かせません。
コマンドブロックの入手方法
基本的にクリエイティブや管理者権限で入手します。
/give @p command_block 1マルチサーバーでは、サーバー設定でコマンドブロックが無効になっている場合があります(後述の server.properties 参照)。
コマンドブロックの種類(3タイプ)
コマンドブロックは「色(種類)」だけでなく、実行方式の設定も重要です。設置してブロックを開くと、次の項目を切り替えられます。
- 常時実行 / レッドストーンが必要:自動で動かすか、信号が来たときだけ動かすか
- 条件付き / 無条件:直前のコマンドが成功したときだけ実行するか
- 遅延(Tick):反復ブロックの実行間隔を調整(重い装置の負荷軽減に有効)
まずは「反復(紫)+常時実行」でループ処理を作り、次に「チェーン(緑)+条件付き」で処理をつなぐと理解しやすいです。
- インパルス(オレンジ):1回だけ実行(ボタン/レバー向き)
- チェーン(緑):連鎖して実行(複数処理を順番に)
- 反復(紫):繰り返し実行(常時処理、監視装置向き)
コマンドブロックは“設定を間違えると動かない”ことが多いので、まずは「インパルス+レッドストーンが必要」で単発実行→動いたらチェーンや反復に進めるのが安全です。
応用テクニック|コマンドを組み合わせた実践例
ここからは「コマンドを組み合わせて装置を作る」イメージを掴むための実践例です。まずは“動く形”を作って、少しずつ条件(セレクター引数)や演出(tellraw/playsoundなど)を足していくと上達します。
ワープ装置(ボタンで指定地点へ)
インパルス(オレンジ)に次を入れてボタン接続:
/tp @p 100 64 -200複数の行き先を作るなら、看板やボタンを並べて、それぞれ別座標の /tp を入れると簡単に“ロビー”が作れます。
踏んだら発動する床(ブロック判定)
反復(紫)に「床のブロック」を判定して発動させます。
/execute as @a at @s if block ~ ~-1 ~ gold_block run say ゴールドの上にいます床ブロックを「圧力板」「色付きブロック」などにすれば、複数のトリガーを分けられます。
自動回復ゾーン(範囲内のプレイヤーに効果付与)
例:半径5ブロック以内のプレイヤーへ再生効果(反復で常時実行)
/effect give @a[distance=..5] regeneration 2 0 true最後の true はパーティクル非表示(環境により挙動が異なる場合あり)。演出を見せたいなら省略します。
ボス戦闘システム(条件で段階変化)
スコアボードを使うと、HPや討伐数などを条件に“フェーズ変化”が作れます。例として「一定回数攻撃されたら雷演出」のような仕組みも可能です。
ここは発展要素なので、まずは tag で対象を固定し、/execute と /effect を組み合わせて段階演出を作るのが理解しやすいです。
チャット演出(tellraw等)
Java版の /tellraw はJSON形式でリッチな表示ができます(クリックイベントなど)。統合版は対応範囲が異なるため、簡易表示から始めると安全です。
Java版と統合版のコマンド違い
Java版と統合版は似ているようで、細部の仕様が異なります。特に /execute、アイテム指定(NBT)、一部コマンドの有無で躓きやすいです。
座標指定の違い
- Java版:整数座標(ブロック位置)を基本に扱うコマンドが多い
- 統合版:小数(浮動小数点)を受け付けるコマンドが多い
- Java版:ローカル座標(
^ ^ ^)が使用可能(視線方向基準) - 統合版:ローカル座標(
^ ^ ^)も多くのコマンドで使用可能。相対座標(~ ~ ~)と使い分ける
アイテム指定(NBT)の違い
Java版は /give などでNBTタグを直接付けられるため、カスタムアイテムが作りやすいです。統合版はNBTを直接編集できないことが多く、/enchant や /replaceitem 等で段階的に設定します。
セレクター引数の対応差
- Java版:
nbt=、predicate=など高度な条件指定が可能 - 統合版:基本的なセレクター引数中心(環境・バージョンで差あり)
execute コマンドの違い
現在は統合版も「新構文」のexecuteが主流です。基本は as(実行者)と at(実行位置)を理解すると、ほとんどの装置が作れます。
Java版:条件分岐が豊富
/execute as @a at @s if block ~ ~-1 ~ diamond_block run say ダイヤブロックの上にいます統合版:現行は新構文が基準
/execute as @a at @s if block ~ ~-1 ~ diamond_block run say ダイヤブロックの上にいます
(補足:古い統合版では detect を使う旧構文が残っている場合があります。新しいワールドや現行バージョンは上の「新構文」を基準にしてください)データパックとアドオンの違い
Java版:データパックで機能拡張
- カスタムファンクション、ルートテーブル、レシピなどをJSONで定義
- ワールドの
datapacksフォルダに配置
統合版:アドオン(ビヘイビア/リソースパック)で拡張
- ビヘイビアパック:モブやアイテムの挙動変更
- リソースパック:見た目(テクスチャ/音/UI)変更
マイクラサーバーでコマンドを活用する方法
マルチプレイでは「誰がどこまでコマンドを使えるか」を設計するのが重要です。OP権限や権限レベルを適切に設定すると、荒らし対策にもなります。
サーバーでのOP権限の付与
Java版サーバーはコンソールまたはサーバー内でOPを付与します。
op PlayerNameホスティングサービスの管理画面(コンソール)から付与する形式も一般的です。
OP権限レベルの設定
Java版は権限レベル(1~4)でできることが変わります。必要最小限の権限にしておくと安全です。
サーバー設定ファイルの編集
Java版サーバーは主に server.properties(設定)と ops.json(OP権限)を中心に管理します。enable-command-block=true は「コマンドブロックを使う・使わない」を決める重要項目です。
統合版(BDS)は server.properties に加えて、権限を管理する permissions.json などのファイルを使います。ホスティングサービスによっては管理画面からON/OFFを切り替えられる場合もあるので、まずは「管理パネルの設定項目」を確認するとスムーズです。
例:コマンドブロックを有効化(Java版)
enable-command-block=trueマルチプレイサーバーでの便利なコマンド
/whitelist add:参加者をホワイトリストに追加(荒らし対策)/gamerule keepInventory true:イベント向けに死亡ロストを防ぐ/time set day:常に昼にして建築向けに/gamerule doDaylightCycle false:時間停止(撮影向け)
マイクラサーバーを快適に運用するためのVPS・ホスティングサービス
同時接続人数が増えるほど、CPU性能・メモリ・ストレージ速度・回線品質が重要になります。MOD導入やプラグイン運用をするなら、特にメモリ確保は優先です。

